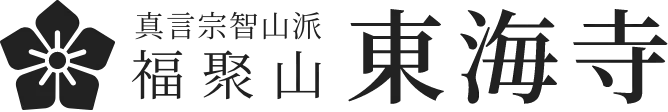栃木県宇都宮市にある真言宗智山派のお寺です。
正式名称は「福聚山 宝珠院 東海寺(ふくじゅさん ほうしゅいん とうかいじ)」と申します。
ご本尊は「阿弥陀如来(あみだにょらい)」です。
寺伝によると、鎌倉時代の寛喜二年(1230年)小山城主朝比奈兼秀の孫和田新兵衛朝盛が出家し円覚に改め寺を開創しました。
室町時代に水戸の佐竹氏が時の金山奉行に命じて篠井金山を開発させ、その時佐竹氏は虚空に満つる無限の財宝が授かるようにと念持物であった虚空蔵を奉安する堂宇を建立している。
水戸の東海寺村にちなみ寺号を東海寺としたという。
天正十年(1582年)以降寺運は衰微し荒廃するが、正保年間(1644~1647年)に僧・実雅が再興し伽藍は整備されました。

-
年間行事
-
1月1日 | 元朝大護摩供 |
|---|---|
2月3日 | 佐貫観音節分会大護摩供 |
3月20日 | 春季彼岸会 |
6月 第1日曜日 | 柴燈大護摩供火渡り修行 |
8月2日 | 大施餓鬼会 |
8月13日 | 初盆法要 |
9月23日 | 秋季彼岸会 |
12月31日 | 除夜の鐘 |
毎月 第4日曜日 | 写経会 |
-
別院 佐貫観音院
-
佐貫石仏について
ここ鬼怒川左岸にそびえる大岸壁は、石英粗面岩で岸壁の中腹に線刻されている石仏が智拳印を結ぶ金剛界の大日如来坐像である。
風化がすすみ石仏の全体像を拝むことは困難になっているが、像高は約18.2メートルの巨像であり顔面の長さは約3メートル幅約1.64メートルである。
造像年代については、石仏の右肩上に奥の院、または大悲窟とよばれる小洞窟があるが、この奥の院がご開帳された明治12年(1879年)にここから銅版阿弥陀曼荼羅(昭和62年12月栃木県文化財に指定)が発見されているが、この曼荼羅の裏面に「下野国氏家群讃岐郷巌堀修造事勧進沙門満阿弥陀仏大檀那右兵衛尉橘公頼 建保五年丁丑二月彼岸第三日 金銅仏奉掘出畢」とあり「巌堀修造」と石仏の製作が何らかのかかわりがあるとするならば、建保5年(1217年)に近い年代に石仏も造像されていたと推考される。
なお、「橘公頼」は宇都宮朝綱の三男であり「氏家郡」という郡名はないが氏家二四郷を氏家郡と私称していたのかも知れない。
また、この奥の院は六十二年毎に一度開帳されてきたとつたえられている。